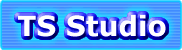
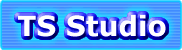 |
|
| Top > アーカイブ > 医学・医療情報 > 医学部講義関連資料 > 薬理学実習(平滑筋)レポート |
更新日:2022/2/5 薬理学実習(平滑筋)レポート★作成時点での情報・記事であり,最新の情報ではありません。 【実験目的】この実験では,摘出回腸の筋緊張に及ばす種々の薬剤の効果を調べ,その実験結果から腸管平滑筋における自律神経支配,薬物の作用機序および作用様式について考察する。 【実験方法(実験1・2共通)】
〈実験1〉アセチルコリンの摘出回腸に対する各薬物の効果【実験方法】
【実験結果】1.d-Tbのグラフ(グラフ【1】)
d-ツボクラリンは神経筋接合部遮断薬で,Achの作用を競合的に遮断する(競合性遮断薬)。主に骨格筋に作用し,腸管平滑筋にはあまり影響を与えないので,Achのみを投与したときと変わらないと予想される。実験では,再現性の曲線とd-Tbの曲線との間にあまり差がみられないので,洗浄が不十分だったと考えられる。 2.C6のグラフ(グラフ【2】)
ヘキサメトニウムは神経節遮断薬であり,主にニコチン受容体を遮断する。摘出回腸では,副交感神経節遮断によって,平滑筋緊張と運動は低下すると予想される。しかし実験では,C6を投与した場合のAchによる作用に差は認められなかった。これはAchが平滑筋の神経筋接合部のムスカリン受容体に直接に作用したためであると考えられる。 3.Neosのグラフ(グラフ【3】,管内濃度は5×10-7M)
ネオスチグミンはアセチルコリンエステラーゼ(AhE)の作用を阻害するため,Achの作用を増強し,またニコチン受容体にも直接作用する。そのためAchの用量作用曲線は左にシフトすると予想される。実験では10-7Mでは十分な結果が得られなかったため,5×10-7Mにて実験を行ったところ,予想通りの結果が得られた。 4.Atroのグラフ(グラフ【4】,管内濃度は10-8M)
アトロピンは抗コリン作用薬で,ムスカリン受容体と結合してその活性化を阻害する拮抗阻害薬である。従ってAchの用量作用曲線は右方にシフトすると予想される。実験では予想通りの結果が得られた。 【考察】1.腸管平滑筋における自律神経支配について Neos前処置下でAchの用量作用曲線は左方シフトし,Atro前処置下でAchの用量作用曲線は右方シフトした。従って腸管平滑筋は,コリン作用性の神経(主に副交感神経)によって支配されていることがわかる。 2.アトロピンの拮抗様式について アトロピン前処置の実験において,Achの用量作用曲線は右方シフトし,Ach濃度の十分に高いときには,アトロピン前処置なしの時の筋収縮量とほぼ同じ(最大反応量は同じ)であることから,アトロピンはAchの競合阻害薬である。 3.アセチルコリンの作用部位について 自律神経の化学伝達の種類
摘出回腸では,上の表の薄く塗りつぶした部分のみ存在するので,Achは副交感神経にのみ作用する。AtroはムスカリンRと結合して作用する抗コリン薬であり,C6は神経節のニコチンRに結合して作用する神経節遮断薬である。実験の結果からムスカリンRと結合するAtroでは右方シフトが起こり,ニコチンRと結合するC6では変化がみられないことから,Achの腸管平滑筋収縮作用は,AchがムスカリンRに結合することによって起こる。 4.交感神経の役割を明らかにする実験計画 副交感神経節のうち腸管を支配するものは,壁内神経節でニューロンを代えるためその神経節の作用をみることができる。しかし腸管を支配する交感神経節は,上腸間膜神経節でニューロンを代えるため神経節の作用をみることはできない。 そこで交感神経の示す実験では次のような方法を採る。今回の実験と同じく摘出小腸を用い,実験装置・条件も同様にするが温度を37−38℃にして自律運動を亢進させ,トーヌスを高める。まず腸管にAchを投与して用量作用曲線を描く。次にNEを前処置した後Achの用量作用曲線を描く。 ◇NEによる収縮の阻害がみられたとき 腸管平滑筋のアドレナリンRにNEが直接作用し,Achの収縮作用に拮抗したと考えられる。NEの作用部位を知るために,以下の薬物を前処置した上での用量作用曲線を作成する。 ▼アドレナリン作用薬
▼抗アドレナリン作用薬
▼アドレナリン作用性神経遮断薬
◇NEによる収縮の阻害がみられなかったとき 平滑筋のアドレナリン受容体に対するNEの直接作用はないので,交感神経が副交感神経の活動を支配していることが考えられる。これを実証するためには,まずニコチンを投与してニチコンによる副交感神経節刺激の用量作用曲線を描く。次にNE前処置した後にニコチンを投与し,用量作用曲線を描く。このとき収縮が抑制されていれば,NEが副交感神経節に作用して副交感神経の活動を抑制することがわかる。 5.各種パラメーターの測定 Atro前処置 〈実験2〉ヒスタミンの摘出回腸に対する各薬物の効果【実験方法】
【実験結果】1.シメチジンのグラフ(グラフ【5】)
シメチジンはH2受容体の競合遮断薬であるが,H2受容体は回腸に存在しないため,回腸の平滑筋に影響を与えない。そのためHisのみを投与したときと変わらないと予想れる。シメチジンはH2受容体の競合遮断薬であるが,H2受容体は回腸に存在しないため,回腸の平滑筋に影響を与えない。そのためHisのみを投与したときと変わらないと予想される。事件ではほぼ予想通りの結果が得られた。 2.Dphのグラフ(グラフ【6】)
DphはH1受容体遮断薬であるのでグラフは右方シフトすると予想される。実験ではほぼ予想通りのグラフが得られたが,収縮反応が微弱であるためより濃い濃度のHisを使うと最大反応が得られると予想される。このことからDphは,競合阻害薬であると予想される。 3.Papのグラフ(グラフ【7】)
Papは平滑筋弛緩薬であるのでグラフは右方シフトすると予想される。実験ではほぼ予想通りの結果が得られた。Pap処置後のHisの最大反応は,Hisのみの場合に比べてかなり低くなっていることから,Papは非競合阻害薬であり,H1受容体以外を介して平滑筋弛緩を起こしている。PapはcAMP量を上昇させ,細胞内Ca濃度の上昇を抑制することにより平滑筋を弛緩させる。 4.Atroのグラフ(グラフ【8】)
Atroはムスカリン受容体の阻害薬であり,Hisを用いた今回の実験ではHisの用量作用曲線に変化はみられないと予想される。実験結果はほぼ予想通り大きな変化はみられなかった。 【考察】1.HisのpD2 pD2はED50(最大反応の50%の反応を引き起こすアゴニストの用量)の負の対数である。pD2は10-5と10-4の間にあり,10-5g/mlのところから平均16.6mmのところにあるので,pD2 = -log(A×10-5) = 5+16.6/63 = 5.26 2.Dph,Papの拮抗様式 Dph前処置後のHisの用量作用曲線は,右方シフトするが最大反応は変化しないので,ヒスタミンH1受容体を競合的に阻害する。Papの前処置後のHisの用量作用曲線は,右方シフトし最大反応を低下させるので,ヒスタミンの非競合阻害薬と考えられる。 3.抗ヒスタミン薬のID50を求める実験 ID50とはアゴニストの最大反応を1/2にするアンタゴニストの量である。これを調べるには単独適用法を用いて調べる。 各種濃度のアンタゴニストをまず適用し,洗浄しないで続いて一定濃度のアンタゴニストを加えて反応を観察した後,薬物を洗浄する。アンタゴニストの適用量を変えて実験を繰り返し,アンタゴニストの濃度を横軸に,抑制率(%)を縦軸に片対数用紙にプロットする。抑制率が50%となるときのアンタゴニスト濃度がID50である。 4.生物学的検定の応用 生物学的検定とは,「薬物を一定の条件下で試験動物もしくは細菌などに作用させて検量線を作成し,未知の濃度の薬物濃度を定量する方法」である。腸管を用いた場合について考えると,有機リン中毒患者の血清中のコリンエステラーゼ阻害活性を調べるのに用いられる。 5.ヒスタミンH1・H2受容体についての検討法 Hisのみの用量作用曲線を作成し,次にH1,H2受容体遮断薬を前処置した後のHisの用量作用曲線を作成し,その変化からH1,H2受容体の作用を検討する。使用する薬物としてはH1受容体遮断薬にはジフェンヒドラミンなど,H2受容体遮断薬にはシメチジンなどがある。 受容体遮断薬によってHisの用量作用曲線が右方シフトすれば,その受容体がその作用に関係があると考えられる。同様にしてH1受容体作用薬とH2受容体作用薬による用量作用曲線の関係をみてもよい。 6.DphのpA2 pA2はアゴニストの用量作用曲線を2倍だけ高用量に平行移動させるのに必要な競合的アンタゴニストのモル濃度の負対数である。 pA2 = pA+log(x-1) = -log(3×10-8)+log(45-1) = 8+0.45+1.49 = 9.94 |
Copyright(C) 1997-2022 Suzumura Tomohiro All rights reserved.