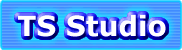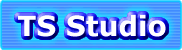更新日:2022/2/3
2000年度BSL資料 マイナー系診療科2
★作成時点での情報・記事であり,最新の情報ではありません。
臨床検査・病理部・血液内科
病理部では,午前中は若狭先生と病理標本をみて,いろいろと質問されたりします。とにかくありとあらゆる病気なもんで予習なんてしていきようがないし,結構イヤーノートみてこたえてもよさそうなんで,気楽にすることをおすすめします!
午後は2つのグループに分かれて,カルテと標本をみて,どんな病気なのか,どういう病態やったのか,調べさせられます。私のは胸腺腫でした。もうひとつはたしか絨毛癌やったかな?またきいときます。
血液部というところにもいきました。気の毒なくらい狭いです。でも血液型の判定をやって,わりとたのしかったです。
森ノ宮の血液センターでは最後に献血をたのまれます。私はちょうど3日前に抜歯してたのでできず,ちょっと申し訳なかったです。歯科治療はこの日がおわってからにしましょう!!白衣はいりません。血液製剤づくりの見学のときはかしてもらえます。あとはひたすらいろんなひとのはなしを聞くだけです。血液センターだけあって,何度か缶のお茶やコーヒーをだしてもらえます!ねむくなっても,5人だけなので,いねむりもできないし,コーヒーはありがたかったです。
病理部は,ちゃんと面倒みてくれます。学生慣れしてるというか。若狭先生もすごく親切だし,八幡先生なんかは,口調も面白くて,笑いながら勉強できます。聞けば聞くだけ教えてくれるし,なんといっても他と違うところは,学生同士で「ぶつぶつ」言ってることでも,「え,今なんて言ったの?」って聞いてくれて,「こんなアホなこときいていいんかな」って思って「ぶつぶつ」言ってた事も質問として解決してくれるような親切さです。だからちょっとシャイな人でも気兼ねしないと思います。
学生に与えられる症例は,だいたい同じみたいです。私たちのは,胸腺腫です。んで,手術して,9日後に死亡した例です。この人は,心筋梗塞をどうも術中におこしたのであろう,ということをプレパラートを見て判断させられます。と言っても,本を見ながら調べてみなさい,って感じなので,即答する必要はまったくありません。心筋梗塞の時間的経過と組織像の関係は病理の教科書なら載っているそうです。予習する必要はありませんけど,見ておいてもいいかも。んで,心筋梗塞の際に血液検査で何を見たらいいか,(術後で。)答えを一応書いておきますが,CKのMB型というやつみたいです。それから,胸腺腫とセミノーマ,リンフォーマの鑑別点を調べさせられます。んで,この症例にはアスベスト肺がみられます。なんか,鉄アレイ型のを見つければいいようです。このために肺気腫になっているらしいです。
こんなところでしょうか。どこの科にも「つつく」先生はいますけど,「あんたらだって学生の時は知らんかったやろ」って言いそうになるのをこらえて,がんばりましょ!
病理部〜臨床検査医学の5/8〜5/12のBSLの内容を報告します。
月曜日と水曜日は病理部でした。これに関しては既にメールでまわっています。火曜日は臨床検査医学でした。朝は中先生と「お話会」 and 血糖測定をしました。「お話会」が結構つらいけど(中先生曰く「ロジカルに物事を考えるべし。」⇒医学的知識について細々聞かれるのとはちょっと違うので予習はできないと思う。)血糖測定はよくわかりました。昼からは血液型の判定方法の実習でした。その場で丁寧に教えてもらえるので
なかなかgoodでした。木曜日は血液内科でした。基本的に放っておかれます。僕らが受け持たせてもらった患者さんはATLの看護婦さんでした。看護婦さんなので医療面
接がスムーズに進みました。金曜日は赤十字血液センターに行ってきました。お客様扱いでこっちが気が引けるくらいでした。資料もきっちりもらえるので僕は有意義だったと思います。最後に献血をしてきました。
- 病理部:月,水(1週目),月(2週目)の計3日。
- 臨床検査部,輸血部:火(1週目)
- 血液内科:木(1週目),火,水,木(2週目)の計4日。
- 総合診療科:火,木(2週目)
- 赤十字血液センター(森ノ宮):金(1週目)
- 医療情報部:金(2週目)
の6つですが,血液内科の先生が,総合診療科,医療情報部もカバーしてると言う感じであまり境界がはっきりしない面がありました。以下和田君や大和さんの報告とかぶるところもあると思いますが,報告します。
- 1. 病理部
- 午前中は基本的に顕微鏡です。若狭先生が病理診断するのを一緒に見て教えてもらいます。大体1回20-40くらいの症例をみました。分からなくても親切に教えてもらえ,いい勉強になりました。year
noteは役に立ちます。午後は,グループごとに割り当てられた剖検症例について勉強します。二週目の月曜日に発表します。Aグループの人は,germ cell
tumorについて少し見ておくといいかもしれませんが,結構教えてくれるし,まあ始まってから勉強しても大丈夫でしょう。あとはカンファレンスがある時は,それに出ることになります。大体5時までには帰れる。
- 2. 臨床検査部,輸血部
- 特に記する事なし。
- 3. 血液内科
- 日野先生は最初とっつきにくかったけど,聞けばしっかりと教えてくださいます。余裕があったら白血病,悪性リンパ腫,あと骨髄移植とか,末梢血幹細胞輸血とかのへんをみといたらいいかも。2週目の木曜日の午前中に,グループごとに割り当てられた患者さんについて,日野先生の前で発表します。日野先生は,教科書的なことではなく,どんな治療が考えられるかということについての議論を望まれているようでした。各自レポート提出がありますが,これは後から出しにいってもいいようです。内容,形式についても特に指示はなく好きに書いたらいいようでした。あと,全員ではありませんが,骨髄穿刺や動脈血採血とかさせてもらえます。やりかたとか見といたらいいかも。午後は基本的にほっとかれるので,早く帰ろうと思えば帰れると思います。
- 4. 総合診療科
- 予診をとらせてもらいます。問診後,血液検査をすることが多いので,検査値に付いて少し見といたらいいかも。2週目木曜日の午後は,疫学(有病率とか特異度とか)の講義でした。
- 5. 血液センター(森ノ宮)
- 講義と見学。4時半ごろ終わって,最後に献血(希望者のみ)。
- 6. 医療情報部
- 午前中は総合診療科で外来。予診をとらせてもらう。午後はメディックスでインターネット。5時ごろ終わり。
病理部
午前中はひたすら顕微鏡を覗きます。睡魔と闘ってください。若狭先生はやい!よく聞いてると本当はとっても分かりやすいです。(たまに質問がきますが,イヤーノートでは半分ぐらいしかわかりません。)私はけっこう楽しかったです。八幡(はば)先生の気が変ってなかったら,標本実習は前の班のと同じでしょう。
血液内科
学生担当の日野先生はめがねがチャームポイント。こちらから聞かない限り教えてくれない。ゆえば,動脈採血もやらしてくれるし,総診では血圧はもちろん神経学的所見までとらしてくれる。(私はできなかったけど。)でも,いわゆる親切な先生ではない。病棟のときはさっさと帰るのがいいです。2週目の木曜,カンファレンスは9時30分からですが,9時には行きましょう。回診があります。私はほっていかれました。
総合診療科
午前中に2回あります。血内の日に1回と最後の金曜です。金曜の朴先生はパソコンも教えてくれるんですが,気さくな先生です。どんどん発言しましょう!微熱の続くはたちの女子学生は私の一言で婦人科受診することになりました。……ほんとによかったの?
老年科・神経内科
老年科,神経内科についての情報をお伝えします。
スケジュールは,午前(AM 9:00-)と午後(PM 1:30-)に分かれます。午前は12時前には終わり,めしが食われへんとかいうことはありません。午後もそんなに遅くなるということはなく,大体3:30から5:00位までには終わります。
内容についてですが,まず始めに,A,B各グループに1人ずつの患者が割り当てられます。主に午前の時間を使って割り当てられた患者に対し,問診,一般内科的所見,神経学的所見をとっていくのですが,まず先生から説明があって,それから実際の所見の取り方などを実際に行ってくれると思うので,参考になると思います。また,解らないことは先生に質問すれば多分答えてくれると思います。問診とか所見がまとまれば,先生に報告します。そこで,アドバイスや足りない部分の指摘を受け,足りない部分はまた患者に聞きにいきます。午前は毎日この繰り返しです。老年科,神経内科のBSL終了後1週間以内に症例レポートと課題レポートを提出します。
次いで,午後の内容ですが各曜日ごとに以下のようになっています。
- 月曜:症例報告会,回診,抄読会
- 症例報告会では学生は座ってるだけでいいです。ここで貰えるプリントはレポートの書き方とかの参考になります。また,自分の担当の患者の情報が得られるかもしれません。抄読会も座ってるだけでいいです。回診では患者の疾患とかについて簡単な質問をされます。
- 火曜:自律神経検査
- 簡単な説明の後で,心電図から自律神経の機能を調べる検査を実際にやってみます。質問されます。
- 水曜:弘済院の見学
- 弘済院の見学で,痴呆について勉強させてもらえるようなのですが,弘済院側の学生を受け入れる体勢がまだ整ってないとかで,うちの班は中止になりました。
- 木曜:骨粗鬆症,骨量検査法
- 骨粗鬆症と骨量検査法について勉強し,実際に自分の骨量を測ります。質問されます。
- 金曜:まとめ
- そのまんまです。
老年科,神経内科のBSLでのストレスを軽減したい人は,病棟を回る前にBSL前の実習でやった脳神経の所見の取り方をおさらいしとくといいかもしれません。あと,病棟の患者はほとんどが高齢者で,実際は複数の病気を抱えていることが多いので症例をまとめる際には結構幅広い内科の知識が求められることもあります。
法医学・環境衛生学・公衆衛生学
法医学・環境衛生学・公衆衛生学につきましてレポートいたします。
それでは本題に入ります。まずは法医から。
おしなべて言えばラクだと思います。予習も特に必要ないと思います。ただし毎日レポートが課せられるので、ためるとちょっとしんどいかもしれません。どの先生も丁寧に教えてくれるためきっと実りのあるものになるでしょう。今までの講義ノートはけっこう役に立ちますから、持参すれば効率よく進められるかもしれません。監察医局の見学は「行きたくない」と言ってる人もいるようですが、急死の所見などを観察することができ、有意義なものだと思います。
続いて環境衛生学。
企業の見学(産業医の仕事を見に行く)は予習不要です。救急車同乗実習は楽しみにしてる人も多いと思いますが、たいがいはたいしたことのない傷病が多いようです。僕は映画「救命士」のニコラス・ケイジのような気分で出向いたのですが、ちょっと期待してたものと違いました(一刻を争う傷病を期待するというのもよくないことですが…)。事前にテキストを渡され予習しておくように言われましたが、内容としては救急の行岡先生の講義の復習をしておくぐらいで充分だと思います。レポートは課せられますが、たいしたことはありません。
最後に公衆衛生学。
予習は不要だと思いますが、余裕のある人は廣田教授のインフルエンザの講義の復習と、M3時に履修した疫学の復習をしておけばいいと思います。レポートもまったくありません。
以上です。他の科に比べればラクだと思いますが、外での実習時には、服装と時間には注意を払ってください。
法医学・環境衛生・公衆衛生について、はっきりいってこの2週間はBSLというよりは、毎日が実験、見学で3年の後期のようでした。
でも、「医者ってこんな仕事もあるんだ!」という感動が毎日あり、貴重な体験ができました。こういう医者の世界は、ほとんどの人がもう二度と見る機会がないと思われるので、きちんとこの機会に勉強しておきましょう。では、具体的な内容について書いてみます。
法医学
- ・死亡診断書・死体検案書の書き方
-
- ・アルコールの吸収・代謝について
- 班員の2人がそれぞれビールを2缶のみ、尿中・血中のアルコール濃度を測定する。(おつまみ代として藤田先生が500円くれる!)(うちの班の某君はすっかり酔っ払ってしまった!)
- ・監察医見学
- 検死の様子を見学する。(最初はショックで倒れそうになるが、死因をつきとめるという、大切な現場なので、亡くなった人のために、頑張って向き合いましょう)
- ・血液型判定について
- おもて試験・うら試験の原理について、必ず予習しましょう。
あと、余力があれば、Lewis型についても。
環境衛生
- ・産業医見学
- 企業専属の医者のお話を現地まで行って聞くことが出来る。
- ・救急実習
- 行く場所によって、出動回数はまちまち。消防署は男の人ばかりで、独特の雰囲気なので、女の子は心して行きましょう。なお、出動の際には全速力で走るので、運動靴で行きましょう。
- ・あとは、ガチャコのガチャガチャしたお話をたくさん聞ける!!
公衆衛生
- ・西成の社会医療センター見学
- 天王寺から歩いていける。女の子は、一人で行かないように!!
- ・老人福祉施設見学
- ずーっと放っておかれたので、ひたすら老人と話した。痴呆老人とそうでない老人の区別を瞬時に出来るようにしましょう。痴呆老人とばかり話していると、そうでない人にも同じ話し方をしてしまい、大変失礼になってしまう!!
- ・統計演習
- ぜんぜんわからへんかった!!分かりたい人は、オッズ比、交絡因子、マンテル・ヘンツェル法etcについて予復習しておきましょう。
全体的に、実験・見学と言っても楽なもので、4時か5時には帰れます。ただ、法医学のレポートが毎日あるので、まめに書いておかないと、あとで痛い目にあいます。あと、注意点としては、見学が多いので、
- 社会人としての一般的なマナー(挨拶、荷物を机に置かないなど)
- 服装(男の子は背広、女の子はパンツスーツあるいはそれに代わるもの)
が大切かと思われます。
えーっと,法医学については,前の班の情報どうりでした。朝9時から夕方5時まで。空き時間はレポート作成に励んで…。ただ,付け加えようと思うのは,法医学全体として時間に厳しいということです。特に朝は遅れないよう注意しましょう。午後の集合時間もそうです。実際怒られて,減点ものやなと言われたりもしました。朝に要注意です!
あまり,報告することがないのですが。
月曜日…9:00〜12:00インフルエンザの話です。13:00〜15:00オッズ比とかの計算をやります。
火曜日…うちの班は,生駒の「竜間の郷」に行きました。とってもヒマで,先生のお話に付き合った,という感じでした。入所者の方としゃべるということもありませんでした。先生は,少し独特な方で,話があちこちとびます。介護保険について,学びました。それからここは,山の上で,路駐する所もなさそうだったので,車は,やめといたほうがいいです。駅から,バスがあります。昼食に,病院食を出して下さいます。
水曜日…9:00〜12:00産業医の先生が話をして下さいます。うちの班は,松下電池へ,行きました。お昼おごってくれます。13:30〜16:00ガチャコの話です。たえるのみ。
木曜日…8:40〜15:00救急車同乗の日です。楽しみのしている方も多いでしょう。ただ,出動回数は,行く所(1人ずつ違う)によって違い,1回の人もいれば6回の人もいました。16:00〜17:00ガチャコによるまとめでした。
金曜日…10:00〜12:00社会医療センターです。入り口がわかりにくいので,駅でまちあわせて,みんなで,行くのがいいです。迷うと,かなり,心細くなりそう。穏やかな口調の先生で,少し眠くなります。13:00〜16:00黒田先生,圓藤先生によるまとめでした。圓藤先生は,思ってたよりも良かったです。
公衆衛生と環境衛生についてほうこうくします。
- 月曜日
- 午前,伊達先生の講義
午後,山○先生の講義(最低だー。本人がわかってない。)
- 火曜日
- 老人保健施設見学(うちは箕面)
千里中央9時15分のバスでぎりぎりです。(しかもバス停なかなかみつけにくい。5番乗り場やったと思う。)適当に回ってって感じです。
*近くにスーパーがあるから車でもいけると思う。昼食はお金を払ったら出るけど,近くにローソン,セブン・イレブンあり。
- 水曜日
- 産業医(うちは,大阪鉛錫と日本農薬)
汚れてもいい服でいくべき。鉛錫はかなりやばい。阪神千船からは,15分位かかります。昼食は日本農薬で弁当が無料ででます。また,帰りはタクシーで学校まで送ってもらえます。
- 木曜日
- 救急車同乗実習(僕は淀川消防署)
御堂筋線西中島南方から15分
昼食は持っていったほうがいいかも。もっていかんでも弁当をたのんでくれます。(有料400円)皆さん親切で面白いかたでした。飲み物には困りません。(運がよければ行った先の病院にのみものがあったり,コーヒーいれたくれたりします)僕の場合,救急講習が某ホテルであったため,準備とかにつきあいつつ,指令があれば出動していたので結構忙しかったです。(ホテルから出動したりもしました。)次は,赤嶺さんが行くはず…(いいとこです)
- 金曜日
- 午前,社会福祉センター(新今宮)…ひたすら退屈。
午後,エンドウ先生と黒田先生のまとめ…今回は黒田先生一人でしたが,ためになりました。
以上,まとまってないですが,参考にできる部分は参考にしてください。現地集合が多いので,案外朝が早くしんどかったです。では,あと少しがんばりましょう。
|