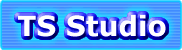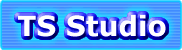更新日:2022/2/3
2000年度BSL資料 マイナー系診療科1
★作成時点での情報・記事であり,最新の情報ではありません。
眼科
一日目の午前中は軽い説明と目隠しをして病棟を歩かされました。目の見えない人の気持ちを知るというものです。十時から始まって十一時には終わりました。担当は助教授の白木先生です。昼からは一時に外来に集合で,視力検査と屈折の検査の実習で学生同士で実際やりました。説明もわかりやすくしてくれるので安心です。ここの担当は田渕先生で,若目でしゃべりやすいです。最後に各々の担当患者の紹介があります。ここは,各々担当の先生が違うんですが,僕の担当は河野先生でした。二日目には,自分でその患者に問診をしなければなりません。あと二班目からは,最後にプレゼンテーションがあるそうです。
二日目は,午前中は十時から外来で前日同様眼底検査などの実習。担当も同じ田渕先生です。午後からは,各自担当患者にアナムネ(問診のようなもの)をとりにいきます。まあ,症状や病歴などを聞きつつ基本的には患者さんとお話するだけです。
二日とも3時くらいにはおわりました。
さて,眼科についてですが,4人(または5人)に一人一人の先生がつきます。眼科の病棟には1〜5グループに分かれて先生の名前が書いてあったのでそれに我々が入っているという感じです。
まず,1週目は検査の実習が多くて,結構すぐ終わったりします。検査の実習はだいたい斑全員でします。(実習スケジュールにかかれているものは)このとき,あらかじめ実習しなければならない検査項目を書いたプリントを渡されているのでした検査の欄をサインしてもらって,2週間で全部します。半分以上はついている先生と一緒にするので,みんなとはすすみ具合が違ってきたりします。
検査の実習のすすみ具合はその先生のやる気の程度によるのでやる気のない先生のときは積極的にアプローチした方がいいでしょう。
病棟では一人の患者さんを受け持ちます。その患者さんの病態についてはそれから調べればいいので勉強していく必要はないかも。
最後の最後の金曜日にはプレゼンテーションがあり受け持ち患者さんのことについて発表しなければいけないのですが,そこではまあまあつっこまれます。三木教授をはじめ10人ぐらいの先生が質問をしようと手ぐすねを引いています(我々の時は後で歓送迎会があったので,質問は控えめだった。)。最後の水曜日,木曜日ぐらいからレポートの準備をし始めます。(カルテを写したり)
簡単に言うとこんなんです。眼科の先生は女性の先生はかなり面倒見がいいのですが,男性の先生のなかにたまに愛想のない,というかうーん,いったら分かります。
眼科です。
眼科は,一人一人に担当の先生がつき,担当患者が一人割り当てられます。担当の先生は,男の先生と女の先生がふたりずつでした。僕の担当の先生は,河野先生という男の先生で,面倒見がいい先生とはいい難い先生っです。とりあえず,自分から話し掛けていかないと,向こうからのアプローチは期待できません。とても,忙しそうですが,こっちがだまってるとほっとかれます。診察を見ているときでもこっちから質問でもしていかないと寒い時間が流れます。
眼科は,最後にプレゼンがあります。河野先生にあたるとカルテを自分で解読しないといけません。わからない単語くらいは,教えてくれますが,質問はしにくい雰囲気です。
あと,眼科では,検査を見なければなりません。表があって,見た検査のところにサインをもらわなければなりません。もし,担当の先生が,あまりやる気がなく,サインがうまりそうになければ,外来に入る田渕先生か木村先生(ともに男)に頼めばやってくれます。もし,河野先生について困ったらその下についている松本先生(女の先生)をたよりましょう。あと,残りの担当の先生については,もう一人の男の先生はいい人そうだけどあまりしゃべらないそうです。女の先生二人(生駒先生と柳原先生)は,丁寧に教えてくれるそうです。まあ,しんどさ的には楽です。
眼科について報告いたします。うちの病院での重要な疾患は,
です。カンファレンスの担当になる患者さんは,恐らくこのうちのどれかでしょう。講義や検査の説明も,これらの疾患に関するするものになってくるので,上の4つを事前に予習しておくとよいと思います。予習ですが,100%は解説が少なすぎて何がなんだかわからないので,図書館で「標準眼科学」を借りていきましょう。また,上のそれぞれの疾患については,分冊の「図解」シリーズがあるのでそちらもよいです。これにはオペの方法もよく書いてあります。
実習では眼底観察がとても難しいです。「これは後々にも役に立つので,できるようになっておいてください」といわれましたが,結局できませんでした。田淵先生の教えてくださるこつをしっかり聞いて,がんばってください。
二週目以降は,「担当の先生の指導」という形になるので,先生によってはとてもひまになります。やることの無い人は,外来の初診を見学してみるのはどうでしょうか。他の外来は,すでにわかっている病気のフォローアップという形なので,同じような病気が多いですが,初心では結構いろんな病気を見ることができます。また,初診ではDrが一から所見を取って診断をつけるので,それらの手法を学べます。これは他の科でもいえることだと思います。
話は変わりますが,眼科は命にかかわる疾患が無いので,他の科と違って,患者さんとも割と楽にお話できるような気がします。患者さんと話す練習にもなりそうです。
後,カンファレンスですが,一人5分だけなので,要領よくやりましょう。質問はかなり厳しいことを突っ込まれました。答えられないときは素直に「わかりません」といって,教えてもらうほうが得なような気がします。
さて今回は眼科についてお知らせいたします。
眼科は先生達が4つのグループに分かれており,学生は一人ずつ各グループに所属し,一人の患者さんについて問診,OPE,診察,検査などに立ち会います。 その他に学生全員で見学する検査:視力検査,眼エコー,斜視外来,眼循環検査,レーザーの授業(尾花先生…質問に答えられへんと気まずい…)などです。行動は基本的にグループごとになるので他のグループのことはあまりわかりませんが,大ざっぱな情報として忙しさはグループによって変わってきます。1グループが一番忙しく,Y原先生に引きずり回されるといった感じです。渋谷によると担当患者でもないOPEにガンガン入れられるそうです。2グループはオラが入りましたが,一番楽でした。昼から来た日も何回かありました。2グループの上の先生はけっこう忙しいので大体は研修医の中倉先生が面倒を見てくれます。中倉先生は親切で,何でも教えてくれます。オラのスキー部の先輩です。3,4グループの情報はあまりわかりませんが,1グループよりはましやと思います3グループの研修医の山崎先生も口は悪いですが面倒見がいいです。4グループは尾花先生の機嫌を損ねないように注意しましょう。なお,グループの割り当てはローテーションで変わるそうです。
担当患者さんのレポートを書いて,それを最後の金曜日にプレゼンします。画像の説明などけっこうつっこまれるのであらかじめ担当の先生に質問したりして用意しておきましょう。なお,レポートには患者さんの心情を詳しく書かんとあかんので問診の時に色々質問しましょう。
耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科について独断と偏見で言わせて貰えば,実習そのものは楽です。先生は皆さん親切で,尋ねればいろいろ教えてくれます。それに,オペでもいろいろ教えてくれるので,別に何の予習もいらんと言えんこともありません。が,画像診断の練習がしたければ,頭頸部の解剖,特に,中耳腔・副鼻腔を含む断面の解剖を予習するとよくわかります。
耳鼻咽喉科はどうも医局員が少ないようで,先生方は忙しいので学生は結構浮いてます。では,具体的にさぼってもOKなものは(但し,当然全員がサボるとまずい),『病棟』と書かれている時間,それと,『教授回診』の時間です。オペは面白い点もあるので,あまりサボることはお薦めできません。それと,聴力・平衡機能検査実習は,教えてくれる先生が出席印を捺すのでサボれません。まあ,あんまりギャーギャー言う先生はいません。橋本先生・松本先生・高山先生・井口先生・久保先生がおそらくメインに学生を見てくれると思います(他の班はどうなるか分かりませんが)。特に,橋本先生は,出席印を都合して下さる素晴らしい先生なので,できるだけ話しかけると特?
耳鼻科についてお知らせしたいと思います。
課題は2つあって,1つ目が英語の論文の発表。2つ目が手術症例のプレゼンテーションです。英語の論文は2人で1つ担当します。要約をまとめて日本語で言うというものです。非常に多くの先生がたの前で発表するのですが,質問は1つか2つぐらいであっという間に終わりました。あまり変なことは聞かれません。それに対して,手術症例のプレゼンは狭い部屋で行われ,先生が2人しかいなかったので,精神的に楽でした。
CT ,鑑別診断,合併症がヤマでした。そして,「ここはもう少し詳しく調べたほうがいいよ。こういう事も書いておいたほうがいいよ。」と言われる程度。といったように,あまりきついものではありませんでした。あと,末期癌の患者さんを1人受け持って,その人のことで少し感想を聞かれました。
皮膚科
皮膚科について書きます。まず予定表との変更点として,初日の集合時間は8時40分に皮膚科外来にということです。
ほんで,2週間の実習ですが,基本的に午前中は外来で見学です。特に予診をとらされるといったことはありませんが,最終日に36人分の病名と治療などをレポートとして提出させられますので,メモなどを取りつつ過ごします。名前だけ聞いたことがあるような疾患を実際に見れるので,勉強になります。
午後は病棟で,一人あたり一人の患者さんをあてがわれるので,その患者さんの病気を調べたり,カルテをみたり,患者さんとお話ししたり…皮膚科でもやっぱりカンファレンスでの発表と,レポートの提出をさせられるので,適当にカルテをみたり,教科書で調べたり,先生にきいたりしました。
先生方は本当にいい先生が多くて,質問には親切に教えてくれました。でも基本的に学生はじゃまなのか,用事がなくなると,すぐに帰れます。平均3時くらいに帰れてたんじゃないでしょうか?カンファレンスの日は5時まで帰れませんでしたが…
オペも2週間に1度だけ,しかも午前中だけでした。糸を切ったり,血をふいたりさせてもらえ,**さんは皮膚を縫わせてもらったそうです。
基本的に楽でしたが,最終日のテストが,ちょっとやっかいでした。テストは,スライドを見て,皮診と鑑別疾患を述べるというテストでした。ちなみにスライドは大量のスライドの中から各自が4枚選び,3問正解で合格です。僕達は'皮膚病アトラス'の過去に出題された病気(去年の情報)について写真を見て答えられるように,覚えました。出題される写真は,典型的な症状のものなのでわかりやすくできてるのですが,鑑別疾患,例えば紫斑だったらそれがアナフィラクトイド紫斑であったとしても,他にどんな病気が考えられるか,を答えられるようにしておく必要があります。あと有名な疾患については,いろいろ聞かれたりもしました。臓器別講義の出席回数がヒントに変わるので,きちんと出席していれば,誘導尋問のような感じで答えられそうです。でも出席回数2,3回でもきちんと答えられれば,通っていました。落ちても,いつでも再試を受けれるようです。4人とも合格しましたし,2週目ぐらいから勉強しても間に合うと思います。
〜昨年出題されたといわれている問題〜
接触皮膚炎・アトピー性皮膚炎・貨幣状皮膚炎・自家感作性皮膚炎・鬱滞性皮膚炎・乾皮症・多形滲出性紅斑・結節性紅斑・糖尿病性壊疽・網状皮斑・レイノー・SLE・DLE・SSC・皮膚筋炎・アナフィラクトイド紫斑・ベーチェット病・環状肉芽腫・血管拡張性肉芽腫・色素性乾皮症・薬疹・固定薬疹・天疱瘡・水疱性類天疱瘡・瘢痕性類天疱瘡・掌蹠膿疱症・魚鱗癬・扁平苔癬・アミロイドーシス・尋常性白斑・肝斑・弾力繊維性仮性黄色腫・黒色表皮腫・ばち状指・表皮母斑・脂腺母斑・扁平母斑・母斑細胞母斑・蒙古斑・青色母斑・太田母斑・血管拡張性母斑・Sturge-Weber・Klipple-Weber・レックリングハウゼン病・プリングル病・色素失調症・Peutz-jeghers・粉瘤・基底細胞上皮腫・ページェット病・有棘細胞癌・軟繊維腫・ケロイド・菌状息肉症・単純性疱疹・カポジ水痘様発疹症・帯状疱疹・ウイルス性乳頭腫・伝染性軟属腫・SSSS・丹毒・ハンセン病・梅毒・白癬・ケルズス・尋常性ざ瘡・円形脱毛症・匙状爪・フォアダイス状態
〜今回新たに発見された問題〜
Werner症候群・苺状血管腫・悪性黒色腫
泌尿器科
UROのクライマックスといえばやはり,教授との面接でしょう。(それ以外はまったくもってNP:non problem。これよくカルテにかいてるよなあ。)本来なら最終日に行うのですが,教授が来週海外へ行かれるため,今週と入れ替わりになり,一週目の金曜である本日教授室に行ってまいりました。
教授といえばおなじみ,岸本先生です。整形の山野教授と並んで,おそれおおい人物の一人ですが,そのかたとじきじきにお話をいただくということで,私はかなり前の日くらいから緊張していました。勉強も自分の受け持ちの患者さんの疾患について,何でもいいから調べてこいと言われていたので,まあ,てきとうにですがノートとかにまとめて準備していきました。いよいよ部屋に案内されて…。
まず,あいさつは基本ですね。席につくなり,
「みんな勉強してんか?BSL初めてやから,泌尿器に関しては完璧ではないにしても,一応,臓器別試験みんな通ってここに来てるんやろ?それに,基礎(医学)は完璧やな?」
私らはそんな完璧なはずもなく,正直に,
「あ,いや,試験勉強はしましたが,忘れているところもあると思います…。」
というと,そんなんじゃいかん,という話の流れになりまして…。
「医者になって,忘れていました,なんて通用すると思うか!」
「…………」
「今,マスコミでは医療ミスで騒がれてるが,どう思う?」
「…………」
「ミスを極力少なくしようと努力するのは当然や。しかし,それでミスは絶対犯さないという自信があるか?」
「…………」
そういったふうな話がずっと続きました。長きにわたる経験をお持ちの先生は,医者の目を通したこの問題の見方を教えてくれました。確かに私たちが今,耳にする医療ミスの問題は,マスコミサイドの視点からみたとらえ方になっています。最善を尽くした上で,それでもミスはおこってしまう。そんな時自分自身が公に訴えられたらどうするか。医者になるのは遠い話だと,あまり考えたことのなかった私には,結構切実に受け止めなければならず,そしてもっとそういったところに関心をもっていかなければならないと思いました。それに関連して,保険の話…,などいろんなことをおしえてくれましたが,私はあまりにも基礎知識がなく,右から左という感じでした。だめっすなあー。
以上,かなり個人の意見も聞かれつつ,ありがたいお話をいただきました。意見は自分の思うことなら何でも言っていいと思います。それがたとえ先生の意見とは違っていても,爆発することはないです。ただ,自分の意見がしっかりといえない医学部生に不満を感じているようでした。どうやらおとといに見たニュースステーションに出てた一年目公務員がしっかりと現状をふまえた上で意見を述べていたようで,その人物にかなり好印象をもったらしく,うちらは同年代として比べられてしまった。そりゃ,この時分に公務員になれるほどの人やもんなあ。しっかりしてるはずやわ。
次に,自分の受け持ち患者さんの症例報告と関連事項を一人づつ言って,それに対してみんなでディスカッションするというものがあります。どんなに低レベルなディスカッションでも先生は聞いてくれていて,間違っているところ,足りないところを補うという形で説明してくれました。
そうですね,みっちり二時間半。やられてしまいました。みんなのおなかからぐーぐーという音が聞こえつつ,でもみんな頑張って目を輝かせて話を聞きました。とりあえず,<てきとうな>やる気を見せるといいようです。これは多すぎても少なすぎてもいけません。
ちなみに英語できかれるというシーンはまったく出てきませんでしたよ。でも,来週の医局会は「It is」の英語でもいいからやってみろと言われましたが…。
泌尿器科のインプレ
先生
学生側から見ても親切な先生ばかりです。つっこんできても,分からなければ親切に説明してくださる先生ばかりです。ただ,どこでもそうだと思いますが外来,病棟などで忙しいときはこちらも気を使いましょう。
- 山本先生
- 最初のガイダンスで講義をしてくれました。ESWLでも講義を受けました。
- 中谷先生
- 腎移植のレクチャーを受けました。"あつい"先生です。
- 武本先生
- 人工腎室におられる。副甲状腺機能亢進症のレクチャーを受けました。どんどん質問しましょう。
- 川嶋先生
- のほほんとした雰囲気の先生です。マリグナントのレクチャーを受けました。
- 池本先生
- 忙しい先生ですが,丁寧に教えてくれます。
- 土田先生
- 人工腎室の先生。勧誘されます。患者との対応に注目。
- 吉村先生
- ひげの先生。プレゼンの時はそこそこつっこんできます。
- 杉村先生
- あまり接していないので分かりませんが,学生に優しいです。
- 甲野先生
- 教授回診の際教授からつっこまれてもいろいろ教えてフォローしてくれました。
- 呉先生
- ゴーちゃんと呼ばれている先生です。先生が暇なときには質問しましょう。
- 岡田先生
- 人当たりがよく,バリバリの臨床といった先生です。こちらが分からなくても丁寧に説明してくれます。
- 吉田先生
- とても忙しそうな先生。質問の時はタイミングを見計らいましょう。
- 山口先生
- 外からの先生。エコーの実習をしてくれます。厳しめに教えてくれます。
- 伊藤先生
- 外からの先生。外来でウロダイナミクス,NGBのレクチャーをしてくれます。質問すると鬱陶しがられるそうです。
- 金川先生
- レントゲン室で担当だった先生。画像の読影のポイントを教わります。それ以外は世間話。
オペ
開腹を伴う全摘術以外は0.5〜3時間です。ちなみに僕は膀胱全摘+リンパ節隔清+回腸導管増設の患者さんの担当だったので,9時から8時の11時間でした(5時には帰りましたが)。鈎引きを手伝う場合があります。細かい小手術(血管吻合術,IVR,焼灼術,TUR等)がみれて,盛りだくさんでおもしろかったです。
教授
岸本教授:入局者がゼロだったせいか,今年は優しいそうです。とある先生がおっ
しゃってましたが……。BSLまとめと教授回診で一緒になります。突如英語でしゃべりだしたり,質問をふっかけてきたりしますが分からなくても,説教が終わるのを待つだけです。今回は後半,学会のため不在だったので,英語でのプレゼンもなしでした。
プレゼン
読影の際,胸部単純,KUB,DIPなどは異常部位はもちろんですが,ルーチンで行うべきオリエンテーションはできるようにしておきましょう。教授がおられる場合は英語でしなければならない場合があるそうです。ポイントはとにかく画像診断です。泌尿器に関わること以外は省略して,スピーディーに終わらせましょう。
外来
先生が一番忙しい時間。ナースも忙しそうなのでじゃまにならない程度に質問しましょう。直腸診を体験できます。その際,患者さんは痛がることが多いのできちんとお礼をしましょう。
放射線科
さて,放射線医学では,患者さんに接するよりも,寧ろ画像に接する方が多いです。担当の先生の話を聞きながら,エックス線単純撮影画像,CT画像,MRI画像などを見て所見を述べてゆく形式の実習が主でした。
水曜日には山田教授の回診がありました。慢性肝疾患の患者さんが多かったです。その時に,慢性肝障害の身体所見(例えば,蜘蛛状血管腫,手掌紅斑,女性化乳房)などについて尋ねられました。来週の水曜日(26日)には,入院患者さんに関する5分間程度のプレゼンテーションをすることになっています。今の所,いずれの日も放射線医学の実習は午後3時頃には終了しています。
全体を通して言えばけっこうラクです。1週目の水曜日以外は3時から3時半頃に終わります。1週目の水曜日ですが,与えられた患者さんのカルテや画像を読まないといけないので,患者さんにもよりますがけっこう遅くなることもあります。2週目の水曜日にはその患者さんの病態や治療方法について,先生(神納先生)に説明しなければなりませんが,(もちろん)日本語でいいですし,先生は1人だけだし,おまけに優しい先生なので,何も問題はありません。
予習としては,余裕があれば解剖の復習をしておけば役に立つと思いますが,していかなくても丁寧に教えてもらえるので特に気にすることはないと思います。実際,僕はまったく予習しませんでした。その代わりというか,復習に力を入れるのが得策かと思われます。BSLで観た画像を家で教科書(『解剖学講義』など)を見て復習していくと理解が深まると思います。それと授業で配布されたプリントも復習の際役に立ちました。
(保証はしませんが)欠席していても,2週目の午後担当のカワベ先生はその分のサインをしてくれるみたいです。だから休みたい人は休んでもいいかもしれません。ただ,どの先生も非常に内容の濃いBSLをしてくれるので個人的には休まない方がいいかと思います。以上放射線科の報告でした。
神経精神科
今回,僕のいってた精神科の報告をします。
はっきり言って楽だと思います。先生方はみなさん,穏やかで親切な方ばかりです。少々遅刻しても全く怒られる様子はありません。一日の経過を簡単に言うと,毎日(初日を除く)朝は9時から外来で先生の診察を座ってみているだけです。ただ初診の患者さんがこられると,予診をとってくる必要があります。予診は患者の訴えを聞くことですが,他科での予診とはちょっと勝手が違うのではないでしょうか。と言うのも患者さんによっては(分裂病の方など)訴え自身が意味不明なことがあり,聞いていることに対して答えが返ってくるとは限らないので…。
しかし予診がぜんぜんうまく取れなくても先生は何も言いません。つまり外来での実習の意味は,たくさんの患者を見ることにあります。結構実際に見ると,(言い方は悪いが)面白いです。
午後は1時30分から,先生の講義を聞きます。しかし先生の外来が延びていたりすると,すこし待つことになる。これも質問をしながらのものですが,特に難しいことを聞かれるのではありません。だいたい4時には終わると思います。
これらとは別に,あと患者さんを一人担当して,その方のCase Summaryを作成します。これは,最終日に,切池教授の前では発表することになります。この作成には,患者さんに直接話を聞きに行く必要があります。(過去に,患者と話をせずに作った人がいてこっぴどくしかられたようです。)また,診断や治療方針など主治医の先生に相談しなければ行けません。細かなことも先生に聞きに行くといいでしょう。
発表は,学生同士質問させて,発表者がそれに答える方法で行われます。採点は,発表と質問の両方を参考にするようです。それなら始めから,質問と答えを話し合って決めておくといいのではないでしょうか。ちなみに切池先生は,阪神ファンらしいです。
最後に,チャートを講義に持っていくと進みが速そうでした。(ただし切池先生などの上のほうの先生の前には絶対に持っていかないほうがいいそうです。)講義では,いまいちピンとこなかったことも実際に患者さんを目の前にすると,「ほんまにこんな人っているんやなー」と驚きます。個人的には,軽躁状態の多弁にやられました。
これから精神科まわられる方,まー気楽にやってください。
|